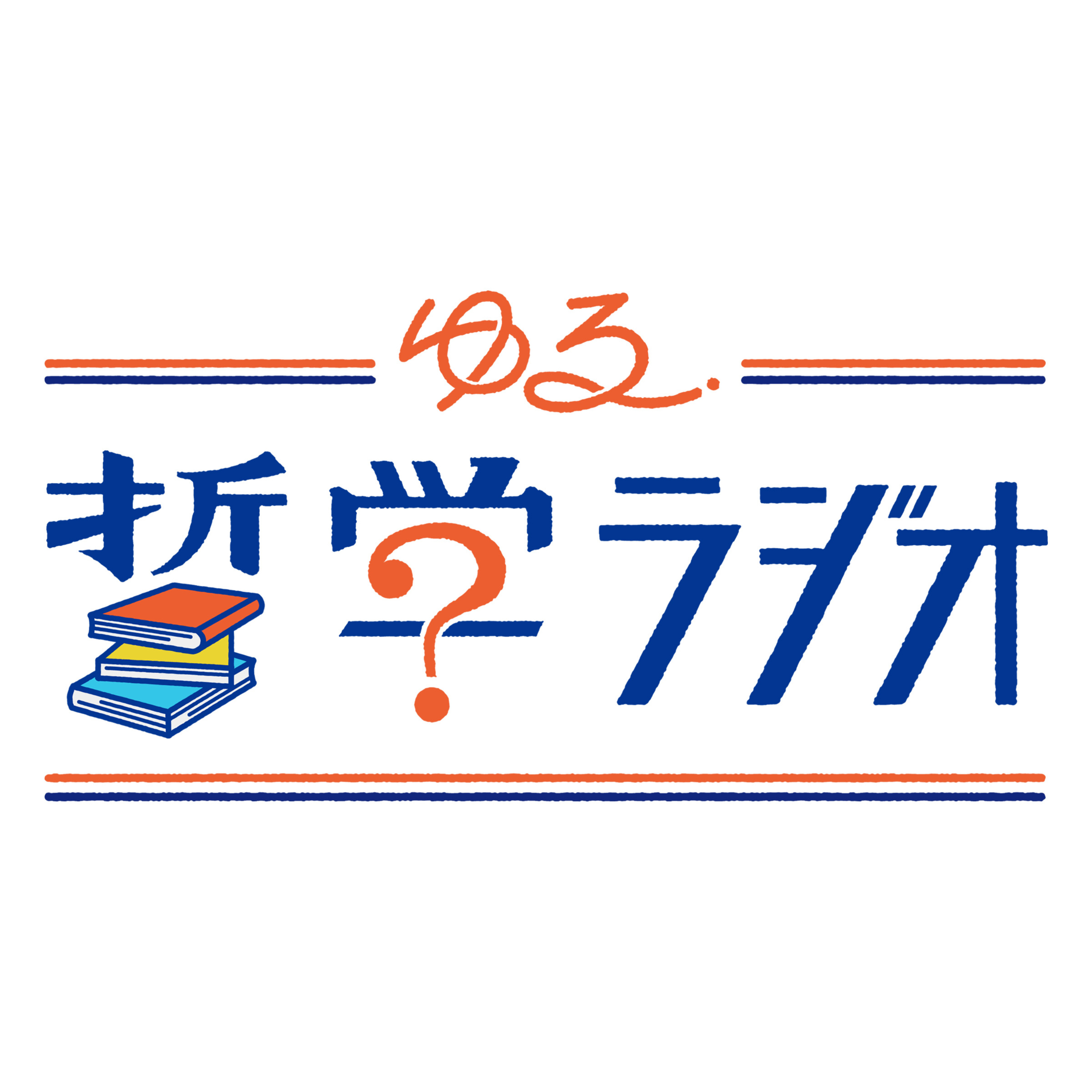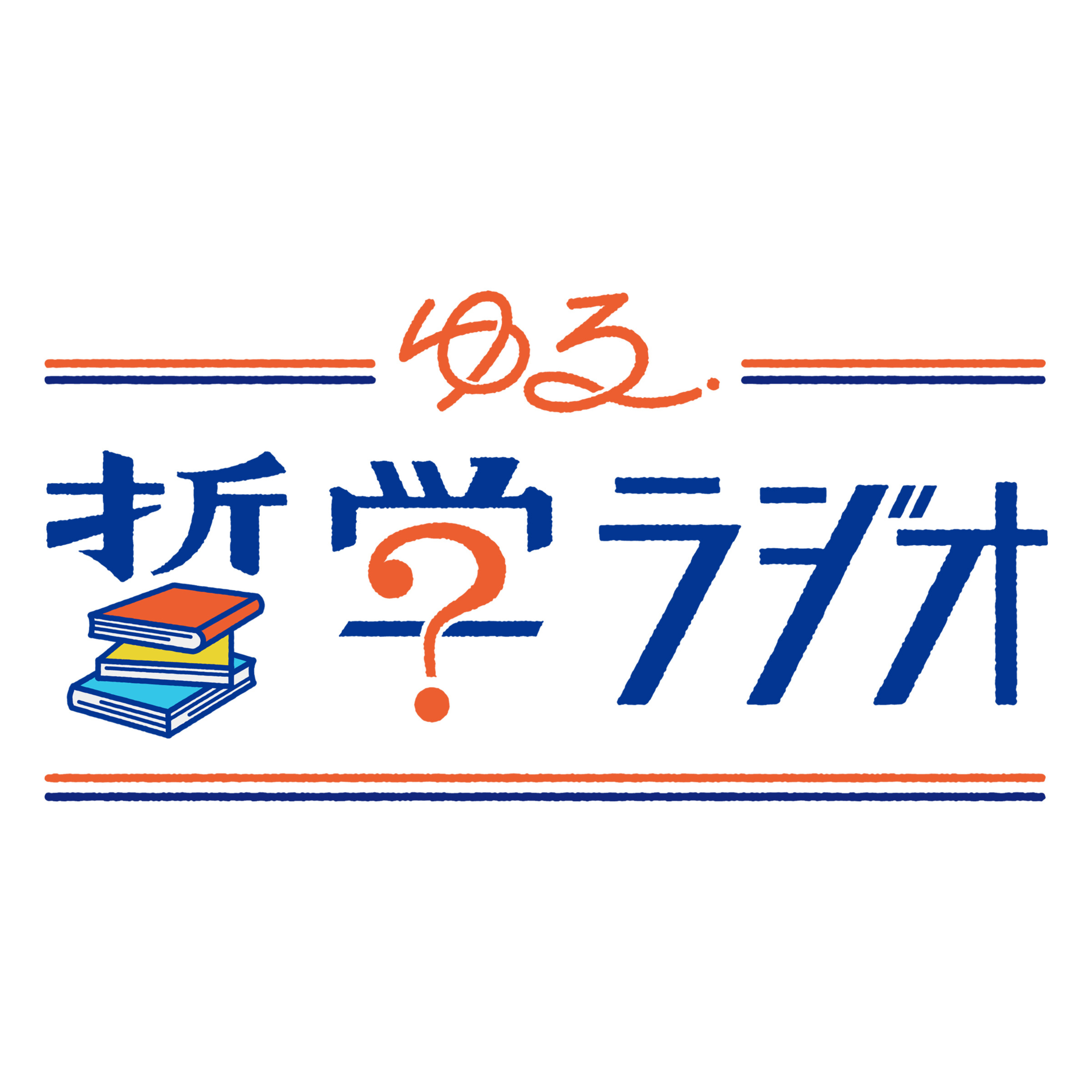
Shownotes Transcript
プラトンの哲学の師匠ソクラテス彼が裁判で死刑になって亡くなったという話を前回したんですけどもソクラテスは民主制のために亡くなったというふうに言って良いかと思いますけどもこれダブルミーニングでして前回の話はソクラテスは民主制だったがために亡くなった
うんそうなんですけど今回はソクラテスは民主制を守るために亡くなったという話をしたいと思います
どういうことやねんとどういうことやねんですね思いますでしょ民主制に殺された男はいですしなんかもう宗具性とかね少なくともプラトンは今の感じだと民主主義よくねえと思ってそうじゃないですかでも殺された当人は民主主義のために死んだんですか民主制を守るために亡くなったという風に言っていいんじゃないかなとソクラテスがそれを望んだ
っていうんじゃなくてその裁判自体がアテナイの民主制という政治体制を守るためにはソクラテスを死刑にせざるを得なかったんじゃないかと実はそんな宗具とかという話ではなくてちゃんとこの国の未来を考えた結果やっぱりソクラテスは死刑になるべきだ
という決断をちゃんと市民は下したんじゃないかそうですかという話もあるんですよ僕はもう完全になんか怪しいおじさんいるから死刑みたいなノリかなと思ってましたけどこれをですね話すためには某ラジオみたいですけど未経年文明の起こりから始めたいと思いますそっちからいくんですかそんなに遡る
おだのぶながの話をするために平安時代に遡りますみたいなこと言っちゃうんですけどでもそれって結構重要で何のかでも歴史ってさ因果関係があるじゃんか
ありますよねインガインガを辿っていくということがねやっぱり歴史を対極的に見るときには必要になってくるので時系列でつながってますしね地理的にもいろいろつながってますからねそうなんですよソクラテスが生まれるずっと前のですね英外界文明とかエジプト文明とかねペルシアメソポタミアとかがいろいろあった中で花開いたミケーネ文明が起こってそこからちょっとね資料がない暗黒時代っていう時代を経るんですけどそこからなんか当てないからポコッとこう
おー
当時ポリスという都市国家今でいう市区町村レベルの国家がいっぱい点在していてアテヌというのがでかい国でしたよと神奈川県ぐらいでしたみたいな話をしたんですけど
当時のメジャーな政治体制何か民主制ってマイナーなんですよ昔は特にそんなイメージがある当てないが民主制で結構栄えた時期でも全体のギリシアのポリスを見ると半数に満たないぐらい
民主制だったのは他は大体王政とか貴族制とかそういう状態だったんですねそんな印象がありますね王政貴族制というのが何なんですかと言いますと王だった
一人のいますね一人ね多分強い名家みたいなのがいたんでしょうね強じ主みたいなのがなんか序盤で戦争とか活躍した一家とかいたんでしょうねヒーローみたいな人とかいたんでしょうねそういう人を王様として祭り上げて王家代々続いてその家の人らが世事を行うという基本世襲みたいな感じ
でね貴族制というのはちょっと王の下ぐらいになるけど 名家が何個かんそれぞれ金持ちの名家がそれぞれ偉いんだよねまあそうそれぞれ偉いし武器を持っていたうんこれが重要なポイントではい まあ世界史をねやってセンター試験
3 年連続 100 戦の 3 年連続じゃない 1 年だけ最後の 1 年だけ最後の 1 年だけ満点取った吉野部さんですねでもすごいことですよねまあもうはるか昔の話ですよね金持ちであるということが戦力を持ってますよということに直接つながっていた時代でございますなんででしょうか
教科書的な回答かもしれないですが戦争をするには武器も食料も含めてですけどとりあえず金がかかるじゃないですか武器ですよね特に裸一貫で突撃してってもねレスリングみたいなことはできるかもしれないですけど殴り合いはできるかもしれないですけど一個剣とか槍持ってたら勝てないわけなんで戦争にて戦えるということは武器を持っているということなのでもちろんお金がないと戦うことすらできない戦争行っても邪魔者でしかないと
犬児にしかしない犬児にしかしない口べらしにしかならない感じになっちゃいますもんねそうなんですよその当時の戦争って例えば馬とかさあとは戦車うんうんうん
馬が引っ張るような戦車とかあとは普通に剣とか盾とかそういうのがお金がかかったと戦争して国を守って戦火を立てるというのは貴族だけに許されたお金がないと皮切ることができないんですよねそうなんですよ特権だったんですよそういう人たちが国を守ってくれた自分たちの領土を守ってくれたからその人たちに政治を任せようと
まあ気持ちはわかりますよね命を張って戦ってくれた人が政治を動かす責任も権利もあるみたいな発想はまあまあまあ確かに国も守ってないのに動かそうとすんなよみたいなねお前何したんだよそうそう国のためにお前が何をしたか言ってみろよみたいな命を張ったんかと言われると確かに張った人の方が偉いでございますとはい
言いたくなる気持ちはまあわかりますね当てないとか他の民主制が行われていたというのは何が起こったかというとその変化ですね持続性とかから民主制に変化が起こりましたとこれはねまあもちろんちょっと待って
ご存知だと復習してこれよかったらこうなるんだったらもちろんご存知だと思いますけれども 10 年以上前の記憶ねファランクスというファランクスはい戦い方が出てきたわけですねなんか習いましたよ資料集に載ってましたよ民衆たちも頑張って盾とか槍とかを手に入れてそれが集団で集まって結構でっか
でっかい丸い盾と槍的なものを持ってみんなで集まるんですよね 集まって一緒に行進していったら結構隙ないんですよ重装歩兵と言われる 重装歩兵ですな人たちが戦力になったとプラスあとね三段海戦というものも出てきましてありましたね 船ですよね 船です
アテナイは特にすごく海に面していまして地理学的今の流行りのワードで言うと地政学的とか言うんですか地政学とか言いますね地政学的にすごく有利な場所にあったので海戦がめちゃくちゃ強かったとで今までは剣とか戦車とかでわーっと戦って 1 対 1 で戦ってみたいな感じでしたけど三段海戦とかになるともう
漕ぎてそうなんですよボートじゃないですかねでかい船を漕がないといけないそう漕ぐだけで戦力になるんだったら別にお金がなくても漕げはするみたいな肉体一つあれば漕ぐことできますからねみんなでねそういう戦い方の変化が起きたことによって俺たちも国守ってますけどみたいなちゃんと漕ぎましたよなんか聞いたことあるのは当時の船の戦い方も
本当にその船ごと突撃していくみたいなあそうそうそうだから本当に漕ぎ手が重要だったっぽいですよねうん船で戦士がいて乗り込んでやーやーって戦うとかじゃなくて本当に船ごと突撃だから漕ぎ手がもう武器みたいないう世界だったらしいと聞いたことあってあのへさきが金属でできてて突き刺すようにできてるっていうバーンってもうはいガチでねあの英雄たちがあーってキンキン
キンキンみたいな映画の世界じゃなくて物理でドーンみたいなボコボコボコボコボコだったらしいですね結構地中海って金属製のへさきが沈んでるらしいそうなんだ昔の戦争の後でいまだに引き上げられるらしいですよへーそうなんだ古代のへさきが見つかりましたロマンですね結構かっこいいよねなんかねてぐらいやっぱこぎて重要
こぎて重要こぎてがこげばこぐほどスピード上がって強いですからねそれがね民主制を生んだんですね戦力の変化がこういうのって限られた都市国家にしかできないことうーん
例えば三段海戦って多分何百人ぐらい漕ぎて必要なんですよそんなイメージはあるそういう人たちを普通に動員できるというのは規模がでかい都市国家じゃないとできないことだしそもそも船も作れないよねそうドックを整備して作らなきゃいけないし確かに作る場所もない木材とかそういう材料も必要だし色々必要なんですよ職人とかも必要でしょうしね当てないが
先週も言いましたけど地中海の海上交易の中心地だったそれで栄えた国民もめっちゃいたし国民って言い方いいのかな市民都市国家民国とはってなっちゃうのかな市民もいっぱいいたし面積もでかかったこういうでかいとこだったからこそ民主制というのは可能になった
ということなんですけどこれがねそう簡単にはね昔の貴族とかが許してくれないんですよまあそりゃそうですよ特権ですからね今もそうですよ古今東西問わずやっぱり特権ってのがあったら守りたくなるのが人間ですからそれはそんな簡単にね船漕いだくらいで何俺たちと同じ権利持ってると思ってんだよと言いたくなるのはまあわかりますよ
それでねギリシアのアテナの中でも貴族制になったり民主制になったり民主制が定着したと思ったらクーデターが落ちて貴族制になったりとか揺れ動いたんだ揺れ動いたんですよそうなんだねそんなに直線的な進化じゃなくて結構行きつ戻りつここもね血なまぐさい闘争が割と結構あるんですけどあったでしょよそれは
例えばですけど、ミケーネ文明、一番最初はやっぱり王政から始まるんですよね。で、王政から貴族制になったタイミングが面白くて、王がひよわになったから、戦えない軟弱者になったからという理由で、貴族制に変わるんですよ。わかんないけど古代っぽいね。軟弱だからダメって。やっぱね、王は戦闘に立ってたって、
戦ってなんぼみたいな強くあるべきなんだそれがいや戦争とかちょっとみたいな蝶よ花よと言ってるような軟弱な文化系はできないんだね王様って言ったらなんだこの貧弱な王はという風に言って貴族制になりました王政からなるほどね恋がでかいやつらいたんだ力を持ってるやつらがねいたんですよ貴族制なんで名家がいっぱいいたわけですよねその人たちはどうやってその意思決定うん
政治の祭り事をしていたかというと 3 つぐらい役職があってアルコンというやつとバシレウスというやつとポレマルコスというアルコンが執政官政治をやる人バシレウスが祭司官占いとかね祭事をする人神様でね
ポレマルコスが軍の司令官おおというね 3 つをね門罰貴族という風に呼ばれる人たちが選挙だったり中戦だったりとかでやってたわけですよはい名家たち同士でねそうそういう中で浮遊な市民みたいなのも出てきてうん
戦いとかで勝ってとか公益で結構力を蓄えてとかねそういう浮遊な市民が出てきた時になんか俺らも政治参加したいけどなぁみたいなそうですよね時に起こったのがですねソロンの改革という懐かしいソロンの改革あったソロンの改革というのがあって
あって門罰貴族みたいな出生エリート生まれた家の家のエリートから富裕エリートお金を持ってる人が偉いですよという風にしてアルコンとかになれる人の対象範囲を広げたんですよ金さえ持ってりゃってことですよね逆に言うとこのソロンの改革良かれと思ってやったんですけど市民側も貴族側もどっちも嫌いみたいな
ソロン何してくれてんねんみたいなシミン側も?これ何かっていうと俺たちにももうちょっと権利分けてよみたいな分けますよって言った割にはあんまもらえてないシミンとあーそうなんだそこで線引くんだみたいなあー
そこで所得制限引くんだみたいな何百万の壁みたいな感じでね何万に壁引いてもどこかしらは絶対出ますよねっていう人たちとあとやっぱ自分たちが占めてたポストなのにあんな汚れた血のシムたちがみたいなね
ポットでのね突然たまたま金を手に入れたような奴らがって言っちゃうわけですよねだから貴族側もソロンの改革には反対貴族側はわかるわちょっとうーんみたいなことが起こってポストの数は変わりません候補者の数はめっちゃ増えましたポストの数増えないのか増えるわけないもんな明日から将軍 5 人になりましたとかないもんなないんですよこれでバチバチの党派争いが
起こりまして必然です誰がやるみたいなのが起きて政治を行うアルコンという役職が決まらないという事件がですねあら何回か起きます誰か決めたらもうダメだみたいな起きそう決めた瞬間もう爆発しちゃうみたいな近交状態が崩れちゃうみたいなのがあってこれでですねアルコンがいない時期という意味でアン
アルコンということでアナルコンという言葉ができて今のアナーキーの語源になったというふうに言われておりますが無政府主義とかのアナーキーですねあれはアルコンが決まらない状態からアナーキーという言葉が行政を司るアルコンが決まらないだからまさに無政府みたいなまさに無政府状態という混乱状態がここで起きていたわけなんですね超混乱だよね
この語源ネタもう一個追加しますとマラソンってあるじゃないですかありますねあれの名前の語源はご存知ですかなんでマラソンっていうか
地名ですっけマラトンと呼ばれるところになんかすごい男の人が走ってたんですよね頼りを頼りを持って戦争の結果ペルシア戦争っていうギリシャ側とペルシアが戦った戦争があったんですけどペルシア帝国があったんですよでマラトンの戦いとかがあってこの
このマラトンで勝ちましたとやっとでその伝令が 42 キロぐらい走ったんですよ勝ちましたっていう風に言った瞬間死んだみたいなというのがマラソンの語源なんですけどなぜマラトンで戦いが起こったかというですね小ネタがありましてこの時改革とかがいろいろあって
権力者がいろいろ移り変わってたんですよね選手って独裁者みたいなヒッピアスっていう人がいてこの人がまあひどかったんですよそれで他の軍の力も借りてそいつを追放させたんですねひどいぞお前そしたらそのヒッピアスがペルシアに逃げ込んでペルシアの力を借りれば俺はまたギリシアで政治家に帰り咲けると言ってマラトンというところがこのヒッピアスの支持基盤だった
ああそうなんだ氷伝みたいなところでペルシアさんとマラトンに上陸すればいけますみたいなことをこのヒッピアスが言ったらしい今ずっと政治争いみたいになりますけど外の勢力の思惑とかもねもちろんあったでしょうから
ペルシアなんてもう当時で言うと最大の敵ぐらいのそうだね一番怖い超大国超大国しかも王政の超絶王政の超大国ですからねそうするそうそうそこを使ってね母国をね売り払うのかみたいな感じがしますけどそうだからマラソンという競技が今マラソンと呼ばれているのはヒッピアスが追放されて祖国を裏切ったから
ブーブー言っにょぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ
なんだそれ完成の完成の完成の完成ペリクレスが多分最盛期ぐらいのそうだねイメージを覚えるためにペリカンと思うんですよそうですねこれがアテナイの最盛期で実はこれペリカンじゃなくてフクロウの帝国という風に言われていたんですよそうなんだなんかそこまでしてたらいろんな意味でただの語呂合わせだったのかちょっと意味を持ってきますね鳥ではあってるっていう鳥ではあってるっていうねペリカン
ペリカンではなかったよペリカンではなかったフクロウの帝国といってソクラテスの弁明の岩波文庫をお見せしたんですよこの表紙にですねフクロウの金貨が本当だフクロウだはい書いてありますこの金貨を発行して力を蓄えたことによって財政が潤ってフクロウの帝国という風にアテナイはついに言われるようになりますペリクレスの下でただねここからね
暗黒時代ですよやっぱりペリクレスが頂点だから後は下がっていくのみなんですよ頂点と言われてるってことはそういうことですねここからねペロポネソス戦争という戦争が始まりましてスパルタ教育でおなじみのスパルタというところのねペロポネソス同盟というのを組んででアテナイはアテナイでデロス同盟というのを組んでいてそこがね戦うわけですよ最初は
当てないも前線したんだけれどもなかなかね攻めあぐねたりとか作戦失敗したりとかして
これ 27 年も続くんですね戦争がそんなに続いたんだ大戦争なんですよこれペロポネソス戦争アテナイに深い影を落とします何でしょういくつかこのペロポネソス戦争が起こった間にアテナイで清算なことがいろいろ起こりましてアテナイって結構細長い場所だったんですけど港と町のところとちょっと周辺の方に畑とか農園とかが広がってたんですよ
ペリクレスはスパルタという国から攻められるのを恐れて農園とかにいる人たちを街に呼んだんですよ空っぽにしたんですこの領土人がいないように農園で育てている作物がなくなっても港さえあれば海上交易できるから食料不足では陥らないという風に思ってですね麦の穂がなる時期にもうちょっと
で収穫だったのにという畑を捨ててを人々 当てないの都心部に呼び寄せたわけでそこをですねスパルタ軍がやってきてもう もうちょっとで刈り取れた麦に火を放ちあら愛する
我が家を打ち壊しみたいな感じでねアテナイの市民はもう打ちひしがれるわけですよ一言でさペロポネソス戦争とかって歴史で習うけどやっぱり内実を見ていくと結構ねひどい話もあっていろいろあるんだねドロドロと戦争ですからねでも狭い場所に急に人口密度が増えたわけですよアテナイは
そうだよねそこでねパンデミックが起こりますパンデミックはい多くの方が亡くなり疫病が流行っちゃったな疫病が流行ってしまいまして 3 人に 1 人だったかなあー結構な割合だはい亡くなってしまうというですね人は多くてひしめき合ってるしうん
何かわからない疫病が流行っているそうだねというですねことが起こりましてなんか最近になって今のギリシャで地下鉄を掘りますとかってなった時にポッカリ空いた穴が見つかってその中に無造作に捨てられたであろう人骨がいっぱい積み重なってるところがあっておそらくその時の
パンデミックで人々はもう恐れて埋葬というか処理をしたんだろうという風に伝わっている恐怖が伝わってくるところでちなみにこの骨を解析した結果この感染症はチョーチフスであったであろうという風に判明をされておりますこのギリシャ人にとって亡くなった人をちゃんと埋葬できないっていうのは神に対する冒涜そういう考えなんだ
にもなるんですよなんか失礼なことであるみたいな不敬であるみたいなことがアテナイの人たちの中にあったとこのアテナイ人たちの不敬に対する恐れって結構あってペリクレスとかに変わってまあいろいろ世代はあってアルキビアデスというですね選手がまた出てきましてこの人がまあ
美形で演説もうまくて武芸に優れていてみたいなもう最高の完璧な人だったんですよアルキビアデスというタイトルで大河ドラマを作るなら
主演は手越くんとかになるぐらいのなんかちょっと騙されちゃうなみたいな感じのちょっと怪しい感じも甘いマスクのなんかかっこいいから危険だと分かりつつもちょっと行きたくなっちゃう感じねとかっていう感じなんですよアルキビアですって人のイメージとしてはねちょっと遊ばれちゃうかもしんないけどみたいなねでもなんかすげえいいこと言ってんなみたいなねかっけえなみたいな惹かれちゃうなみたいなね
そういう人がね選手として立ちましてこの時ね和平を結んでたんですよスパルタとペロポネソス同盟の人たちとちょっと一旦やめましょうねニキアスの和訳というのがねその時あってニキアスさんがちょっと仲良くしましょうよとかって言って仲良くしてたんですけどちょっと平和になったから今あの
シチリア?うんシチリア島っていうね島当時シキリアとかって言ってましたけどこれちょっと遠征しようみたいなことを言い出してなんでかっていうとシキリアってその時めっちゃ裕福だったんでここさえ手に入れれば食料に困ることはない
っていう状態だったんですよ イタリアンサキッチョですよねイタリアンサキッチョの島ですね近いけど距離割とあるよね 割とある 結構ある 中海は割と渡らないといけないよねその当時の航海技術も結構ある 結構あるよねけどやっぱりその当時飢餓とかも結構あって 食料不足っていうかめちゃめちゃ課題だったんだ めちゃめちゃ課題でその時もなんか東編追放みたいなのは制度としては行われてたんですけど
飢餓という風に書かれた答辺がいっぱい見つかっているんですよ選手とか独裁者を追放するんじゃなくて自分は飢餓を追放したいって言って投票したっていうですね痕跡が遺跡から見つかったりとかしてるんですね本当に願いみたいな感じですねそれぐらい極限状態で
スキリア行けば救われるということをアルキビアで演説をしてじゃあ行こうというふうに言ったんですけどこれが大失敗しそうねじゃあなんで失敗したのみたいなことを考えるとそういえばスキリア遠征軍が行く前に不吉なことあったなみたいなことがあった
遠征軍が出発しようとする直前に宛内市街の家々とか神殿の門とかにですねヘルメスという神の石像が建ってたんですけども何者かが一夜にしてことごとく破壊するという事件が起きて犯人が分かりません
しかもこのですねヘルメスってどういう神様かというと旅人を守護するという役割を持った神様だったんですよそれプラスこのアルキビアデスという人が秘儀秘められた儀式を別荘で茶化すようなイベントをやっていて神様との大切な結びつきをなんか
チャカスイベントをマネっ子みたいなオマージュしてちょっと面白かしくやってみました貴族とかでああーとか言ってたりとかそういうのをアルキビアですが遠征直前にやっていたみたいな垂れ込みもあって手越くんなりやりかねないというのがあってこれなんじゃないかみたいな
シキリア遠征失敗したのはヘルメス神が壊されたりとかその秘技をアルキビアデスが茶化したからじゃないかとかというのがあったんですよ結局アルキビアデスを裁判に呼ぼうってなったんですけど言葉巧みに逃げてアローコとか敵国のですねペロポネソス同盟のスパルタに行って当てないここ弱点なんでここ攻めれば勝てますよみたいな
国売りがちですねいいっすねアテネもことを言って最終的には暗殺されたんですけどアルキビアデスはアルキビアデスの策略によってアテナイというのは最終的に 27 年続いたペロポネソス戦争を敗戦で迎えるんですねいやそいつのせいでもはい
で敗戦しちゃうの? 弱点教えちゃったから 教えちゃったから 弱点教えただけ教えて死んじゃって 死んじゃって 祖国を スパルタに行ったりとかしてスパルタ追われてペルシア行ったりとかして結局暗殺されてしまうんですけどもこのですね不敬 神への不敬とかというのが当てないという共同体を脅かす
すごく重大なことなんじゃないかというのが当てない市民たちの中にあったんですよこれまでもさなんか疫病とかもさ当時からするとさちょっと目に見えない世界だからさ不思議なもしかしたら神様がとかいう話もあっただろうしで今みたいな不敬なやつのせいで遠征失敗したりとかも経験してるとさ飢餓なんでしょもういっぱいいっぱいなわけでしょ
やっぱり神様に対する敬意とかちゃんと持っておかないとアテネがやっていけないよという思いが出てきても不思議じゃないですよねまだまだ悲劇は続きますまだ続くの?アテネに悲劇は続きますもう負けたーじゃからいいじゃんスパルタに負けてちょっとスパルタ教育導入されたりしたのかなちょっと近いというかスパルタの軍の力を盾にですね民主制というのが覆されてまあ
そりゃそうですよスパルタンだって民主党じゃないですからね負けた先ですから敗戦国ですから政治形態変えろよと言われますよそれといってアテナイ市民たちの中で 30 人政権という 30 人の人が政治を行う 30 人政権というのが
突如立ったんですよこの 30 人政権はまれに見る恐怖政治を行いまして宛内の市民たちを恐怖のどん底に落とし入れます何をしたかというと 30 人政権が自分たちに味方する市内派と呼ばれる市内はシティの中ですね市内派と呼ばれる人 3000 人を指定します家庭指定するんだ
味方なんでね東波とか東波ラーサリーとか味方だよとこの市内派 3000 人は他の指定されていない全市民の自由に処刑することができますと
つまり 3000 人プラス 30 人政権バーサス全市民という構図が出来上がり市民の中には親を殺されたり急に兄を殺されたりとか恋人を殺されたりとかということが好然と行われていたらしいですそこからですね民主制側民主派側も
トラシュブロスという強い人が帰ってきてトラシュブロスさんちょっとお願いしますとか言ってこの 30 人制限の戦い勝ちトラシュブロスによる和解が行われるわけなんですねここでじゃあ市内派の 3000 人 30 人制限の首謀者どうするかとそうだね好き勝手しやがってね処刑するのかその家族とかまで処刑しようみたいな話もある中でトラシュブロスさんはいやダメだと
過去に起きた悪しき行いについては全て忘れなさいほら成人ですねというですねトラッシュブロスの大謝礼というのがへー
行われまして思い出してはいけません記憶を抹消してください記憶を抹消するということをギリシャ語でアムネステイヤという風に言っていて今のアムネスティオンシャアムネスティインターナショナルそれの語源になっているのがトラッシュブロスによる和解記憶を抹消せよというものだそうですこれによって
民主制がやっと復活した戻ってきたんだここでソクラテスの裁判が始まりますそのくらいの時期なの?はい結構ペロポネソス戦争が終わって 30 人政権ができて恐怖政治が倒れてトランスの
トラッシュブロスによる和解が行われてソクラテスの裁判が始まりますそうなんだ僕全然さ名前とかもちろんねマランダが覚えてたけど時系列全然わかってなくて前世紀アテネぐらいのイメージ持ってたけど全然そんなことないねボロボロの直後だねじゃあなぜ裁判は行われたのかということをちょっと整理してみましょうはい
前回も言ったんですけどもソクラテスの罪状は神への不敬と青年を堕落させたことでしたアテナイの市民からすると神を信じないということ神を冒涜するということはペロポネソ戦争の悪夢を思い出させることだったんですね
パンデミックの恐怖とかアルキビアデスがヒギの茶化したやったりとかヘルメスシンが割られたりとかということを経験した当てない市民たちにとってはソクラテスの神への冒涜というのは共同体の基礎を揺るがす大事件だった重要事項だった
というわけなんですねプラスソクラテスという人はアルキビアデスの師匠でもあったんですよアルキビアデスはソクラテスの弟子であった
あったしソクラテスと問答したこともあるような人であったしソクラテス自体 30 人政権が指定した 3000 人の市内派この中にソクラテスは含まれているんですよそうなんだ結構権力側というか議長みたいな席に座ることもあったし割と政治の中枢に近かったんですとなるとソクラテスの在場の府警とか青年の堕落とかの他に
おそらく民主派の市民たちによるしない派を許せないというですねおそらくそういう感情があったんじゃないか記憶を消せって言って消せたらねこんなね今世界になってないですからトラッシュブロスのアムネステイヤがあったからそれを公然ということができなかった
のでわざわざ神への父兄と青年の堕落ちなみに青年の堕落というのもアニュトスという人がソクラテスを起訴するんですけどこういう人ね川職人の家の人で息子がね結構賢い子だったんですよ
よでソクラテスと問答してたらそのお父さんに僕川職人にならないみたいなあらはいお前は川職人の子に生まれたんだから川職人になりなさいよみたいなこと言ってそしたらなんかソクラテスが来て君のお子さんはすごく優秀だからこういう問答をしてね学問を探求した方がいいよみたいなことを
いや川職人なんてみたいなこと言ってそれが良くなかったんでしょうねそういうね家族というのはその当時から共同体の基礎だったんですよ哲学者のヘイゲルという人が彼の自身の哲学史講義という著作の中でソクラテスが死刑になったのは当然であるとなぜなら神の父兄もこういう戦いがあったし
何よりも青年を堕落させたということではなくて家族で取り決められるべきことに対して口出しをしたということがダメだったんだというふうに分析をしたりしているんですだからソクラテスというのはその当時のアテナイの民衆派の市民たちにとっては悪夢の中心メンバーであって
元々ねペロポネソス戦争時代の悪夢を思い出させるような神への冒涜をしたりとか共同体の基礎になる家族というものを分裂させようとするような
危険分子だったんですよなるほどねしかもね茶化したやつの師匠だしねそうそうそうあいつがなんか言ったんじゃない茶化し方をみたいなアルキビアデスがちゃんとしてさえすればアテナイは戦争にここまでひどく負けなかったかもしれないのにじゃあこいつを教育したのは誰なんだとソクラテスというやつがいるらしいしかもあいつはシナイ派だとということがアテナイの民衆派の市民たちにはあった
ソクラテスが死刑になったのは後の西洋哲学においてはキリストの達形と並び称されるような本当はそういう刑に称されるべきではない人を謝って
って記書してしまったという例として挙げられるんですが本当にそうだったんですかということが歴史を見ていくと僕らも貴族派じゃなくて民主派じゃん多分貴族側じゃないじゃん民主派の最下層みたいな立場でしょうよ僕らちょっとやっぱり民主派に堅い歴史がありますありますねなので哲学の始まりとして裁判に行き通ったプラトンのイデア
理想があってみたいなのが価値があります探求しましょう本当かというですね一番最初に触れたニーチェの価値があるというものがなぜ価値があるという風にされてるかそれは無価値によるものであるとルサンチマン円婚によるものであるとこれもなんとなく納得できるような話なんじゃないかなという風に確かにね思っております
今いろいろねソクラテスが死刑に至るまでの経緯とか話しててまあまあもちろん死刑という極刑がねいいか悪いかっていうのはまあ一旦ちょっと置いといて例えばまあ戦争もののアニメとかさガンダムとか僕好きなの見るんですけどいつもあの世界を見ながら忘れちゃいけないなと思うのがめっちゃ人死んでるんですよはい
戦争の話だねガンダムの時代いろんな創作もだし過去の史実とかを見るときもめっちゃ人死んでるじゃないですか僕らって平和な時代生きてるから親を殺された兄弟を殺された恋人を殺されたっていう経験ないけど戦争中っていうのはそういうのがしょっちゅう全然あったし
そういう大切な人が殺されたことないのに想像しただけでものすごく怒りとか湧くじゃない実際殺された人もっとそうでしょうし戦争なんて言ったらもう本当にやりきれない思いを持ってたはずなんですよしかもそれは一人とかじゃないでしょうからねそういう世界を論評してるネット民とかも見てめっちゃ人死んでるの忘れてない?
ってのめっちゃ思う時があって気楽に扱いすぎじゃない信じてのみたいなこれに関しても 20 何年で戦争しててでもうやりきれない思いとかいっぱいしてる中で忘れましょうって偉い人が言ったからまあそう思っていつつも絶対恨みつらみ消えないじゃないですかその中で唯一のさもしかしたら共通の拠り所だったかもしれない神様への信仰とかをさ冒涜するような言葉をねしてしまったり大切な家族うん
悲劇を経て得たもう自分の唯一の余裕この家族をね
一員を当時でいう不良少年にしたようなもんじゃないですかされたらねなんだこいつはって思う怒りみたいなのはね多分僕らが今想像するもののさらに上を行くと思うんでそんな中で裁判したらさ私のやったことはいいことなんで芸品館で食事をさせてくださいとか言われたらさ魚でですよね気持ちをねですよねって思うんですよ本当だから戦争とかね歴史とか勉強するとしょっちゅう起こるから気楽にスルーしがちなんだけどそう
めっちゃ人死んでてそれを想像するとものすごい恨み怒りがあったはずだよねってのはね忘れちゃいけないなとは思うんですよねそう思うとやっぱり死刑が妥当かは知らんけどそのぐらいの怒りが市民たちにあったよねってのは想像を
できますね実はそのプラトンというのも反民主派というわけではないそこまでではないんですけども割と権力者側というか貴族側の人間ではあるので民主派に対して少し思っていたところがあったのかもしれないともしかしたらその裁判の時のさ芸品館で私をすべきだみたいなもさ茶化す意図があったりしたかもしれないそうだねお前ら分かって
僕のやったことはこんなにすごいことなのにみたいな態度があったとかもあるかもしれないですよねだって前言ってたじゃないですか裁判結果がさ最初有罪か無罪かを決めるとき無罪って言ったのが 220 人くらいいたんだけどどう罪を決めるかで死刑に死刑か罰金かみたいなので死刑派が 360 人増えてる無罪って言った人たちが死刑って言っているぐらいのことが裁判で行われちゃったってことですねそういうことですね
これからちょっと哲学史としていろいろ紐解いてはいきたいと思うんですけども単にね時系列バーとか言うんじゃなくてニーチェの視線も一応手に入れてはいるのでちょっと価値を相対化させつつ本当にそうなんだっけみたいなね裏話もちょっとこうやって話していければなという風に今後も思っておりますということでコメント高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします今回これで以上にしたいと思いますありがとうございましたありがとうございましたさて
今週もやってきましたドゥルーズ語りのコーナー具体ワード的抽象ワードひまわり的時間みたいなものを作ってその概念の意味どうやって使うのみたいなのをコメント欄で教えてくださいというものでございますけれども今週の
トゥルーズ語りワードはですね消火器的忘却アムネステイヤーの話もね今日あったのでたまたまですけどちなみに本当にランダムです収録前にランスジェネレーターで出た数字を元にやってるんでたまたまなんですけど消火器的忘却どういうことかね
こうですよというのをぜひコメント欄で教えてくださいベストアンサーはどこか雑談会でまとめてご紹介したいと思いますということでゆる哲学ラジオ以上にしたいと思いますありがとうございました